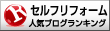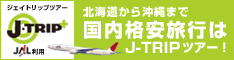今日から、リビングとなる部屋(現在和室)を洋室化していきます。(畳を撤去して、クッションフロアを貼ります。)
リビングの畳を撤去して、土台の状態を確認する
ダイニングの隣の8畳の部屋を洋室化していきます。まずは畳の撤去から。畳の縁をバールのとがっている部分でひっかけて持ち上げます。女性にはかなり重いので、ハードな作業です。
1枚1枚、畳の下に ビニールシートを敷き、引きずって掃き出し窓まで運びました。とりあえず、隣の部屋も洋室化する予定なので、縁側に置いておいて、隣の部屋の分もまとめて処分場まで持って行く予定です。
ビニールシートを敷き、引きずって掃き出し窓まで運びました。とりあえず、隣の部屋も洋室化する予定なので、縁側に置いておいて、隣の部屋の分もまとめて処分場まで持って行く予定です。
さて、畳を 撤去したあとの床の状態を確認しました。多少たわむところがありますが、根太を上手く使って補強すれば活かせると判断。その床を捨て張りとして活用し、上に直接根太を貼っていくことにしました。
撤去したあとの床の状態を確認しました。多少たわむところがありますが、根太を上手く使って補強すれば活かせると判断。その床を捨て張りとして活用し、上に直接根太を貼っていくことにしました。
根太の間には断熱材のスタイロフォームを入れていきます。

捨て張りの上に根太を貼り、(スタイロフォームも間に貼る)その上に合板を貼り、クッションフロアを貼る計画です。
捨て張りの上から敷居までの高さは60mmだったので、根太の太さは45mmにし、針葉樹合板が12mm、クッションフロアが2mmで59mmなので、誤差1mmなの
でほぼ問題なし、…ということで材料を買いに行きました。
今回の材料はこちら
- 針葉樹合板12mm×8枚
- スタイロフォーム40mm4枚
- 45mm角杉材6尺1束4本セット×4束
ちなみに材料は近くのホームセンターにて
針葉樹合板@¥930。スタイロフォーム@¥1530。杉角材1束@¥1097でした。
(2021/3/14時点)
実は45mm角材は4束買いましたが、途中足りなくなったので、追加で更に3束買いました。
そしてスタイロフォームも2枚追加購入しました。ビスは根太打ちには71mmのスリムビス。合板貼りには40mmビスを使用しました。
根太を貼る前にまずは掃除ですね。
- 畳の間だった所に埃がたまっています。
- 掃き掃除しました。
根太を貼っていく

畳を撤去すると敷居の下に隙間が出来ていました。
こちら側の壁だけでなく、四方全ての敷居の下はこんな感じでした。
まずは、隙間を埋めることも兼ねて部屋の外周の根太から貼っていきたいと思います。
- 柱の下にも空間が出来ています。
- 外周の根太をかませて設置
- 互い違いになって空間ができるので
- 角材を削って調整
こんな感じで外周を根太貼りしました。

そして、縦に根太を貼っていきます。
最初はこの細長い空間の中にスタイロフォームを入れていくつもりでしたが、捨て張りの床がところどころたわむので、横にも補助的に根太貼りしました。特に弱いところは更にその中に2本ほど補強しました。(下画像参照)

一度貼った合板を剥がして左のように補強した所が2カ所ほどあります。

途中半分まで完成した写真は撮ってあったのですが、全体が完成した写真を撮り忘れてしまいました。
後で、断熱材を入れた後の全体が撮れているので、それでご勘弁頂ければと思ってます。スミマセン…。
断熱材(スタイロフォーム)を入れる
次にスタイロフォームを裁断しつつ、根太の間に施工していきます。以前、根太を均等に打ってその巾でスタイロフォームを裁断していったところ、やはり素人なので根太が少しでも曲がっていたりズレていたり、またスタイロフォームの切断もカッターでしていたので、かなり曲がっていてなかなか根太の間にが入っていかず、、すごく時間がかかった記憶があったので、今回は根太の空間ごとにサイズを計って入れていきました。
つい最近、YouTubeで「スタイロフォームは丸のこで切るとまっすぐ切れる」という事を学び、実際切ってみると、本当にまっすぐで(もっと早く知りたかった)感動ものでした。
https://www.youtube.com/channel/UC_7xZZTe6Cz3y0xatx8SNPg
- 丸鋸で切断
- 本当に丸鋸で切断するとまっすぐ切れます。感動です!
以下は私流のサイズの測り方(時間はかかるけどサイズはぴったりになります。)
- 1枚のスタイロを空間の端にセットして
- 切っていきたい巾の根太の位置に印付け
- 印同士を定規で合わせて丸のこでカット
- 今度は巾は合っているので浮いた部分の
- 根太の位置に印付けまた、定規で合わせてカット
 この作業をひたすら繰り返す。根太貼り終えてからスタイロを貼り終えるまで大体4時間くらいかかりました。
この作業をひたすら繰り返す。根太貼り終えてからスタイロを貼り終えるまで大体4時間くらいかかりました。
実はこの完成後、下地を合板を張るときにたわみが大きい箇所が2カ所あったので、そこは1度スタイロフォームを取り、根太を3本増強してから、スタイロもそれに合う様に切断して、貼り合わせました。
下地合板を貼る
今度は下地合板を貼っていきます。北側と南側の障子側には出隅や入隅等かなり裁断が面倒なところが多いため、その調整が少なくなるように貼っていきたいと思います。(要するに簡単なところから貼っていきました。)

左の写真から始めてています。
なんでこの様な形になるかというと、では入り口の角の位置をちょうど合板の角で使いたかったからです。
そうすると、出隅をだす回数が1回減るので難易度が少し下がるかと思います。

ちょうどこの角のように合板を使いました。
- 切らずに入れられる合板から施工して
- 出隅が1カ所の所から(やりやすそうな所から)
- 出隅2カ所
- 左半分が終わったので今度は右側
という順で進めて行きます。
今回は出隅の出し方を、私流ですが紹介します。
- まずは合板を最初の出隅の位置で合わせる
- 差し金を使って、奥に入っていく辺の長さを測る
- 差し金の延長線上にさっき測った長さ分の所に印する
- 奥が13,3cmだったので、差し金の26,6cmの所に印を付ける
- 今度は合板が止まっている分(横の辺)の長さを測る
- 今回は13.3×13.8の四角を切り取る(この時に角度が直角とは限らないのであくまでも差し金の延長線上を利用して、正方形ではなく平行四辺形を意識してけがく)
- 丸のこで切断中(菱形の窓の尖ったところに線を合わせて、ゆっくりと切り進める
- 両サイド切り終えましたが、最後残るところはのこぎりで切断
- 1回目の出隅は入りました。
- もう一度今度は敷居に向かっての長さを計っていく。今回は全ての出っ張りが3.3cm奥に入っていくよう切断する
- (同じ作業工程は割愛します)一番奥まで入りましたが…
- ちょっと空間が出来ています。。
- 空間分の長さ分を、出っ張りの所から切り取ります。
- 黒く細い線を引いてある分を切ります。(ちょっと薄くて見にくくてすいません)
- 今度はぴったり合いました。
- アップでも見苦しくなく綺麗に決まりました。

この様な工程を繰り返して、ついに下地が完成しました!!
次回はパテ処理とクッションフロアを貼っていきますが、その前に部屋の壁と天井を綺麗にするので、しばらくは下地のまま、他の作業をします。
…で、その後の続きの記事がこちらです。↓